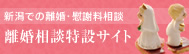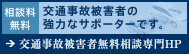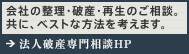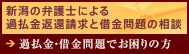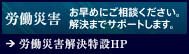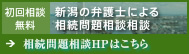最新情報
事務所からの最新情報や法律に関する情報をご紹介します。
労働条件の変更~第3回~(弁護士:下山田 聖)
2021年12月6日
コラム
【過去の記事はこちら】
・労働条件の変更~第1回~
・労働条件の変更~第2回~
はじめに
全3回にわたって、労働条件変更に関する法規制や裁判例を概観してきましたが、本号がその最後の連載となります。
前号では、就業規則により労働条件を労働者に不利益に変更する場合の規律である労契法 10 条に関する裁判例を紹介しました。
本号では、労契法 10 条の条文の各要素について解説します。
労契法 10 条が定める各要素
労契法 10 条は、「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、
①労働者の受ける不利益の程度
②労働条件の変更の必要性
③変更後の就業規則の内容の相当性
④労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情
に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。」と規定しています。
「労働者が受ける不利益の程度」
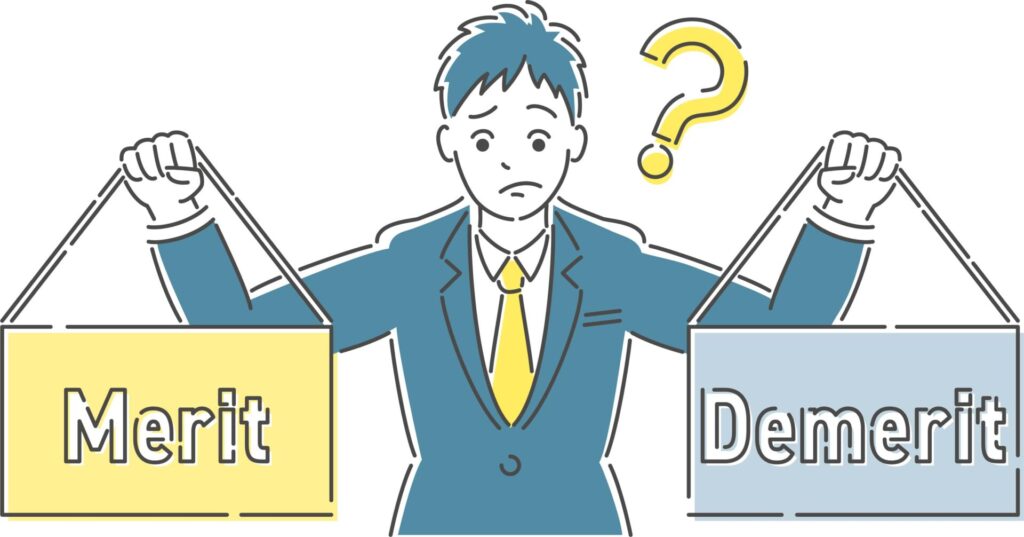
⑴
労働条件の変更により労働者が不利益を受ける場合の典型例は、賃金が減額されることです。
労働者が受ける不利益の程度を判断するに当たっては、賃金減額の程度や全労働者との関連での負担の程度が問題になります。
仮に、賃金減額の割合が同一の事例であっても、当該賃金減額が一定の範囲内の労働者に関するものなのか、全労働者に共通のものなのかによっても判断が変わってきます。
たとえば、高年齢層にのみ不利益を強いるものであるとして、変更の合理性を否定した裁判例もあります。
⑵
変更の合理性が認められるためには、賃金の減額幅が 1 割以下であることも一定の指標とされています。
ただし、これは「変更の合理性」を判断する上での一要素でしかありませんので、1割以下であれば変更の合理性が常に認められるという短絡的な理解に結び付くものではありません。
「労働条件の変更の必要性」
⑴
ここでも、賃金の減額を例にとって解説します。
裁判例では、賃金を含め経費の削減の必要性があったとしても、それだけで直ちに「変更の必要性」を認めないものもあります。
これは、賃金よりも削減すべきものはないのか、賃金を削減することが会社の経営状況の好転に有用なのか、という観点からも検討していることの現れであると思います。
⑵
会社としては、後述する労働組合等の交渉の中でも、賃金削減の必要性等について検討した結果が求められるでしょうから、裁判所における考慮事項を意識した上で、検討結果や交渉状況を目に見える形で残しておくことが必要になってきます。
「変更後の就業規則の内容の相当性」
変更の合理性については、変更後の就業規則の内容の相当性も問われます。
賃金減額を例にとれば、減額後の賃金水準が、同種同業と比較してどの程度のレベルにあるのかという点が、変更後の就業規則それ自体の内容が相当かどうかという点で問題になります。
「労働組合等との交渉の状況」
⑴
裁判例では、不利益変更につき過半数労働組合との合意が得られれば変更の合理性が一応推測されるとされています。
基礎賃金の 1 割前後を減額するとした変更の事例においても、その不利益は少なくないとしつつも、労働者の 99パーセントが加入している労働組合との合意が成立したことに着目して変更の合理性を認めた事例や、仮に組合との同意に至らなかったとしても、約 1 年間組合との交渉を継続していたという姿勢をもって変更の合理性を認めた事例等、様々です。
⑵
裁判例では、労働組合等と「合意」に至ることまで要求されているわけではありませんが、会社の姿勢として、説明義務を尽くし、協議を誠実に実施することが望ましいことはいうまでもありません。
賞与の減額
賃金の減額に類似するものとして、賞与の減額を検討せざるを得ない場面も生じ得ると思います。
この点、賞与の支給自体は法律に定められているものではないため、当然に会社の側に支給義務が生じるものではありません。
また、現実の就業規則上も、「会社の業績等を考慮して支給する。」といった定めをしていることが多いのではないでしょうか。
このような規定内容の場合、就業規則によって労働者に具体的な賞与請求権が発生しているとはいえないため、業績の悪化により賞与を支給しないこととしたとしても、労働条件の不利益変更の問題にはなりません。
しかしながら、例外的に、過去の長期間にわたって同額の賞与を支給し続けているような場合、そのような取扱い自体が「労使慣行」として労働契約の内容となり、この労使慣行と異なる取扱いが不利益変更とされる局面も生じ得ます。
ここでの「労使慣行」は、同種の行為・事実が長期間反復継続されるだけでなく、労使間の規範意識によって支えられていると評価される場合に、「事実たる慣習」として法的効果が認められることになります。
おわりに
以上、全 3 回にわたって労働条件の変更に関する法的規律を解説しました。
この問題に限らずですが、労働法制では基本的に被用者を保護する趣旨での規定が多くあります。
会社の側がこれを無視して労働条件の変更を断行し、結果的にこれが無効となった場合には、会社の側には差額分の賃金の支払など、大きなダメージを受けてしまうこともあります。
リスク回避の問題として、「労働条件の変更は簡単にはできない」ということを念頭に置いていただければ幸いです。
<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2021年9月5日号(vol.260)>
※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。
「企業法務」「雇用問題」「契約書作成」などで群馬県・高崎市内の弁護士をお探しのみなさまは、一新総合法律事務所高崎事務所までどうぞお気軽にお問い合わせください。
★フリーダイヤル 0120-15-4640★